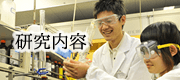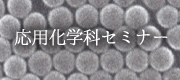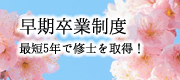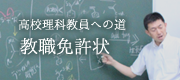Kana M. Sureshan博士講演会
Sureshan 氏は、2002~2004 年、JSPS のポスドクとして反応有機化学研究室に在籍し、在籍中の短期間に驚異的な数の論文を仕上げたスーパードクターで、現在インドで准教授として世界的に活躍している化学者です(こちらを参照)。今回国際会議参加のため来日されるということで、松山に寄っていただき講演してもらえることになりました。なかなかない機会ですので、皆さん是非ご来場ください。
講演タイトル:"Synthesis of Biopolymer Mimics via Topochemical Reactions"
講師:Kana M. Sureshan博士(インド IISER Thiruvananthapuram 准教授)
日時:2018年7月30日(月) 16:30〜17:30
場所:共通講義棟C(工学部講義棟)4F EL43講義室
(担当:林)
夢・化学21 化学への招待 in 愛媛/オープンキャンパス
2018愛媛大学オープンキャンパスにあわせて化学体験実験「夢・化学21 化学への招待 in 愛媛」を今年も開催します。実験を通して化学を体験できるだけでなく、大学で行われている研究や大学生活に触れてみる絶好のチャンスです。
<2019年度より工学部は6学科から1学科9コースへと生まれ変わります>
主催:日本化学会中国四国支部/愛媛大学工学部・理学部
日時:2018年8月8日(水)<工学部会場>(理学部会場は7日(火))
化学・生命科学コース(現:応用化学科)で実施する実験テーマ <参考>本年度のテキスト
- 藍染めにチャレンジ:この実験では、ブルージーンズの染料である「インジゴ」と言う化合物を使って「藍染め」をします。白い布のあちこちを糸でくくって絞り染めにチャレンジ!!結び方が模様の決め手。どんな模様ができるでしょうか?
- 身の回りのミクロな世界をのぞいてみよう:顕微鏡は、私達の身の回りにあるものを何でも拡大し、私達の目で見る世界とはまるで違った新しい世界を見せてくれます。この実験では、電子顕微鏡という高倍率、高分解能の装置を使って、ミクロな世界を覗いてみます。
- 水を吸収する不思議な高分子:紙おむつなどの原料として用いられている吸水性高分子を、化学反応を行って自分で合成してみます。そして、吸水性高分子が実際に水を吸う様子を観察します。吸水性高分子が大量の水を吸収できる原理について学びましょう。
エレクトロクロミック表示素子を作ってみよう:エレクトロクロミック材料は、乾電池などをつなぐことで色が変化する材料です。この材料の一種である酸化タングステンを溶液の状態から透明なガラス板の上に析出させて、実際に色が変化するかどうかを確かめます。【本テーマは中止となりました】- タンパク質を分けてみよう:動物や植物その他の生き物のからだの中では,数千から数万種類のタンパク質が,それぞれ,役割を持ってはたらいています。鶏の卵白に,どんなタンパク質が含まれているのか,調べてみましょう。
- 光によって色が変化する化合物:光によって物質の色が変化する現象を「フォトクロミズム」といいます。この実験ではフォトクロミック分子で作ったインクを使って、光をあてると一瞬で浮かび上がったり、消えたりする絵(スパイの手紙)を描いて、その反応について学びましょう。
(担当:白旗)
講演会
講師の島ノ江先生は、表面・界面の構造や組織などの制御・最適化の重要性に着目した各種機能デバイス開発を行っておられます。講演会ではIoT社会へのガスセンサの展開へ向けた課題抽出と、それを踏まえたセンサ設計の指針について紹介していただきます。
日 時:2018年8月28日(火)16:30–17:50
会 場:工学部4号館1階 E411
講 演:
IoT社会に向けたガスセンサの研究開発
(九州大学大学院総合理工学研究院物質科学部門教授)島ノ江 憲剛 先生
(担当:松口)
PROSセミナー
講 演:植物ホルモンシグナル伝達の構造生物学
講 師:東京大学大学院農学生命科学研究科 特任准教授 宮川 拓也 先生
植物ホルモンは植物体内において様々な酵素の働きにより作られる低分子の有機化合物であり、植物の生長・分化、環境から受けるストレスや病原菌感染に対する防御応答などを制御しています。植物を構成する細胞には、植物ホルモンを受け取って細胞にシグナルを伝える受容体と呼ばれるタンパク質が存在します。近年の構造生物学研究によって、受容体タンパク質がどのようにして特定の植物ホルモンを受け取るのか、またそれにより生理機能がどのように調節されるのか、といったメカニズムが詳細にわかってきました。これらの知見は、植物ホルモン受容体の機能を人為的に調節することで植物に有用な形質を与える技術に応用されつつあります。本セミナーでは、演者らが解析したアブシシン酸受容体、ストリゴラクトン受容体の構造生物学を中心に紹介し、タンパク質の構造情報を活用した植物の生理機能調節への応用についても議論したいと思います。
日 時:2018年9月20日(木)17時から
会 場:愛媛大学共通講義棟C EL16
(担当:澤崎)
第18回中国四国地区高分子材料研究会
主 催:高分子学会中国四国支部
日 時:2018年10月15日(月)14:00–17:40
会 場:総合情報メディアセンターメディアホール
講 演:
- ポリ(キノキサリン-2,3-ジイル)の主鎖らせん不斉制御に基づいた新規キラルマテリアルの創出
(京都大学工学研究科 合成・生物化学専攻)長田 裕也 先生 - バイポーラ電気化学が拓く機能性高分子材料創製
(東京工業大学物質理工学院 応用化学系)稲木 信介 先生 - 高分子粒子安定化ソフト分散体を基盤とする機能性材料の創出
(大阪工業大学工学部 応用化学科)藤井 秀司 先生
(担当:井原)
講演会
講演タイトル:協働金属触媒による有機合成反応
講師:中尾佳亮 教授(京都大学大学院工学研究科)
日時:2018年12月21日(金)17時より
会場:共通講義棟C EL21
(担当:太田)