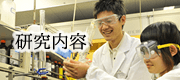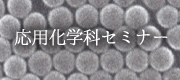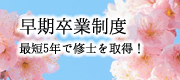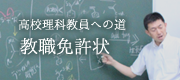応用化学セミナー
応用化学コース/化学・生命科学コースでは学内外の研究者による最先端の研究成果に関する講演会を定期的に開催しており、実施回数は300回を超えました。詳細はこちらをご覧下さい。
夢・化学21 化学への招待 in 愛媛/オープンキャンパス
2025愛媛大学オープンキャンパスにあわせて化学体験実験「夢・化学21 化学への招待 in 愛媛」を今年も開催します。実験を通して化学を体験できるだけでなく、大学で行われている研究や大学生活に触れてみる絶好のチャンスです。多くの高校生のご参加をお待ちしています!
主催:日本化学会中国四国支部/愛媛大学工学部・理学部
日時:8月7日(木)<工学部会場>8日(金)<理学部会場>
工学部工学科で実施する実験テーマ
- 水を吸収する不思議な高分子:紙おむつなどの原料として用いられている吸水性高分子を、化学反応を行って自分で合成してみます。そして、吸水性高分子が実際に水を吸う様子を観察します。吸水性高分子が大量の水を吸収できる原理について学びましょう。
- 光により色の変わる化合物:光によって物質の色が変化する現象を「フォトクロミズム」といいます。この実験ではフォトクロミック分子で作ったインクを使って、光をあてると一瞬で浮かび上がったり、消えたりする絵(スパイの手紙)を描いて、その反応について学びましょう。
- ゲノムDNAを抽出してみよう:私たちヒトを含む全ての生き物は、「遺伝情報」を持っています。タンパク質は、この遺伝情報をもとに合成されます。遺伝情報は、細胞の中にあるゲノムDNA上に書き込まれています。この実験では、細胞からゲノムDNAを抽出して、その性質について学びましょう。
- 藍染めにチャレンジ:この実験では、ブルージーンズの染料である「インジゴ」と言う化合物を使って「藍染め」をします。白い布のあちこちを糸でくくって絞り染めにチャレンジ!!結び方が模様の決め手。どんな模様ができるでしょうか?
- エレクトロクロミック表示素子を作ってみよう~えっ、固体の中をイオンが動く?~:エレクトロクロミック材料は、乾電池などをつなぐことで色が変化する材料です。この材料の一種である酸化タングステンを溶液の状態から透明なガラス板の上に析出させて、実際に色が変化するかどうかを確かめます。
- タンパク質を分けてみよう:動物や植物その他の生き物のからだの中では,数千から数万種類のタンパク質が,それぞれ,役割を持ってはたらいています。鶏の卵白に,どんなタンパク質が含まれているのか,調べてみましょう。
(担当:太田)
講演会
「三次元環状π共役系の合成・構造・機能〜輪と螺旋からなる対称分子が生み出す新機能を目指して〜」
講 師:長谷川 真士 先生(北里大理)
日 時:2025年8月22日(金)16:00-17:30
会 場:共通講義棟C EL44講義室
(担当:御崎)
講演会
「線虫rRNA前駆体のプロセッシングとストレス応答」
講 師:牛田 千里 先生 (弘前大学)
日 時:2025年9月2日(火)14:30-16:00
会 場:共通講義棟C EL16講義室
(担当:冨川)
2025年度中国四国地区高分子講演会(愛媛地区)「高分子合成を基盤とする研究の最先端」
主 催:高分子学会中国四国支部(詳細はこちら)
日 時:2025年9月24日(水)14:30-19:00
会 場:総合情報メディアセンターメディアホール
- 界面光反応に着目した機能性微粒子の開発と環境調和型微粒子への展開
(阪公大院工) 北山 雄己哉 先生 - 変幻自在の機能物質創製に向けた音動的物質工学の開拓:触媒開発からデバイス開発まで
(九大先導研) 本多 智 先生 - 極性ビニルモノマー類の高耐性・高選択的Lewis Pair重合
(名工大院工) 松岡 真一 先生
(担当:井原)
山口和也先生講演会
「複合機能固体触媒による環境調和型脱水素酸化反応の開発」
講 師:山口 和也 先生 (東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻)
日 時:2025年12月23日(火)16:10-17:10
会 場:工学部4号館・1階E411
(担当:八尋)